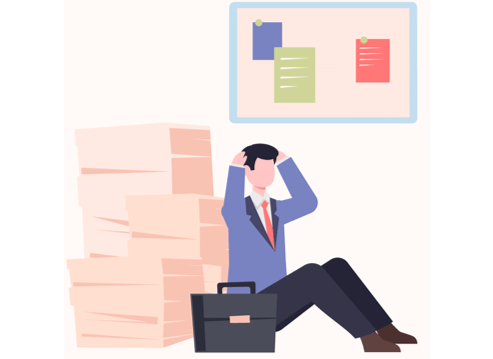僕個人としては、投資を始めるのであれば、投資信託の積立から始めるのが一番手堅く資産を増やせると思っています。
ただ、間違った方法で積立をしてしまうと、本来利益が出るところでマイナスになってしまう可能性があります。
今日は、投資信託の積立がなぜ失敗しにくいのかを説明すると同時に、それでも失敗してしまう人がいる理由を事例を交えてお話しします。

投資信託の積立が失敗しにくい理由
まず初めに投資信託の積立がなぜ失敗しにくいのか、その理由をお話しします。
下の表は、人気の高いインデックスファンドでよく用いられている指数の過去30年間のリターンを表しています。
| 平均利回り | 日経平均 | MSCI ACWI | S&P500 |
| 1年 | +17.9% | +17.6% | +22.7% |
| 3年 | +11.6% | +6.3% | +19.4% |
| 5年 | +12.0% | +11.6% | +22.1% |
| 10年 | +9.3% | +9.3% | +16.9% |
| 15年 | +9.0% | +10.4% | +17.5% |
| 20年 | +6.2% | +8.8% | +11.9% |
| 30年 | +2.1% | +8.0% | +12.0% |
※my index 2024年7月時点

最近は株式市場が好調であるというのも影響していますが、どの期間でみても、プラスになっています。
特に注目すべきは30年平均利回りです。
日経平均は少し心許ないですが、ACWIとS&P500では、年8%、年12%とかなり高い利回りとなっています。
過去30年と言えば、2000年ごろのITバブルの崩壊、2007年ごろのリーマンショック、2020年ごろのコロナショックなど、多くの暴落がありましたが、その暴落を加味しても、平均で見れば、これくらいの利回りと言うことですね。
ですので、オルカンやS&P500と呼ばれるインデックスファンドに長期投資をすれば、利益が期待できる可能性がかなり高いということです。

これだけ明確にデータとして出ているわけですが、なぜ投資信託の積立で失敗してしまう人がいるのでしょうか。
失敗事例① 目先の値動きを気にしすぎる
投資信託の積立で失敗する人の特徴として、自分の運用残高をとにかく気にしてしまう人がいます。
こうなってしまうと、相場が上がっているときは、得した気分になりウキウキしますが、相場が下がったときは、損した気分になり、イライラしてしまいます。
僕も投資を始めたころは、同じ過ちを犯していました。
相場の動きを気にしすぎると、特に下落相場に入った時に、
「これ以上下がったら、積立を続けてもマイナスが膨らむだけじゃないか」
「まだまだ下がる気がする。これ以上損を拡大させないためにも売却しよう」
という様々な負の感情に支配されてしまい、仕事に集中できなかったり、夜寝れなかったりします。

こういう状態に追い込まれると、ほとんどの人はこのストレスから解放されたいが一心で、積み立てをやめてしまい、投資信託を売却してしまいます。
いくら長期で保有をすれば、プラスになっていくと頭ではわかっていても、感情面で耐えられなくなってしまうんですね。
長期で保有するのであれば、そんなに頻繁に見ても仕方がないので、多くても1か月に1回確認すれば十分です。
失敗事例② 無理な金額で積み立てを始めた
これもよくある失敗例です。
複利で資産のシュミレーションをしてみると、毎月5万円、10万円を積立つづけて、年利5%程度で運用ができれば、15年20年でとてつもない金額に資産が膨れ上がります。
それを見て、少し無理をした金額で積立を始めてしまい、初めのころは問題なく積立続けられるものの、結婚や子供が生まれることがきっかけで、月々の出費が嵩み、積立を続けられなくなる人がいます。
積立投資の魅力は何と言っても、中長期で積み立てることで複利の力を最大限に活かすというものです。
ですので、無理のない金額でとにかく長く運用を続けることが何よりも大事です。
失敗事例③ 大暴落で売ってしまう
10年に数回は起こる大暴落ですが、大暴落が来ると、これまでコツコツ積み上げた利益が一瞬でマイナスになるので、「これ以上資産が減らないうちに一度売ってしまったほうがいいのでは?」と考えて、積み立てた投資信託を売却してしまう人がいます。
長期で保有を続ければ、プラスになる確率が高いと頭ではわかっていても、いざ大暴落の最中にいると、「本当に戻るんだろうか」と疑心暗鬼になってしまうのです。
感情的になってしまう局面では、理論的に頭で考えても、どうにも解決することはできません。そのため、相場をあえて見ないようにするのが一番シンプルで効果的な方法になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
結論を一言で言ってしまえば、投資信託の積立で失敗する人と成功する人の差は、積立投資を我慢強く続けられるかという非常にシンプルな結論に帰結します。
しかし、シンプルではあるものの、なかなかこれを我慢強く続けられないのが投資家です。
今日、紹介した投資信託の積立失敗事例を頭の片隅に置いて、同じ過ちを繰り返さないようにしてください。