投資信託の勉強もしたし、いざ投資を始めようと思うけれど、どのタイミングで始めればよいかわからないという相談をよく受けます。
上昇相場の時は「そろそろ下がり始めるんじゃないか」と思いますし、下降相場の時は「まだまだ下がるんじゃないか」と、色々な考えが出てきてしまい、結局なかなかスタートを切れなくなってしまう人もいます。
僕も投資を始めたころは、同じような思いをしたことがあるので、よくこの気持ちはわかります。
投資の基本原理は、安く買って高く売ることですので、相場をしっかり見定めることは非常に重要なことです。
ただ、投資信託に限って言えば、実はタイミングを見計らって売買するメリットはほとんどありません。
それはなぜなのか、今日はお話しします。
投資信託の基本的な商品設計
そもそも投資信託というのは、どういう仕組みの金融商品なのかを、まずしっかり理解することが重要です。
ここでは話をわかりやすくするために投資信託の中身がほぼ株式で構成されている銘柄を例に挙げたいと思います。
最近は、本来の株式投資の考え方ではなく、短期間での利益を狙っていくような株式投資をする人が増えてきています。
そのような人たちは、安く株を買い、値上がりしたタイミングを見計らって、株を売却し、利益を得ることを狙っていますので、相場をとにかく読み切る力、安く仕込むかが運用成績に大きく影響を与えることになります。

しかし、本来の株式投資というのは、皆さんから集めた資金を使って、企業がビジネスを拡大し、利益を増やし、その利益の一部を株主にお礼として還元するというものです。
つまり短期的な利益を狙って売買するものではなく、長期的な利益を期待して投資するものなのです。
株式投資=企業の成長に期待して投資するものですから、株式の集合体ともいえる投資信託もまた、長期目線で企業の成長に期待して投資をするものということですね。
ここから言えることは、投資信託は目先の値動きに心を揺さぶられて、売買をするものではなく、長期的な企業の成長や経済の成長を期待して投資をするものということです。

この点は非常に重要なことですので、ぜひ覚えておいてください。
世界経済は右肩上がりに成長している
投資信託は、企業の長期的な成長を期待して投資をするものだということはわかったと思いますが、世界の経済は果たして成長しているのでしょうか。
それを確認するのに使えるのが、GDP(国内総生産)です。
GDPは、分かりやすく言えば、各国内での企業の儲けの合計値を表す指標だと思ってください。
例えば、主要国のGDPの推移を見てみましょう。
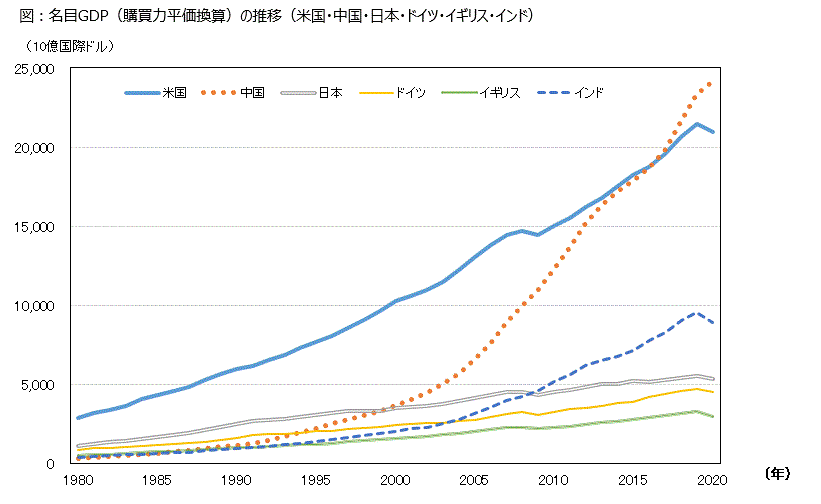
どの国においても、GDPは右肩上がりに成長していることがわかります。
これは言い換えれば、各国の企業の売上の合計値は右肩上がりに伸びていると言い換えることとができます。
企業の売上の増大=企業価値の増大=株価の増大なので、長期的な目線で投資をすれば、株価は上がっていく=株式の集合体である投資信託の価値も増大していくということになるわけです。
ポイント
単一の株式では、右肩上がりの経済成長の恩恵を受けれない可能性もあるが、数百~数千の企業に一度に投資ができる投資信託であれば、この世界経済の成長の恩恵を受けることができる
投資信託は長期運用ではとにかく負けづらい
せっかくですので、もう一つあなたが一歩踏み出すための貴重な情報をご紹介しましょう。
下の表は、国内株式に投資する投資信託の利回りを分析した表を用意しました。
| 平均利回り | 元本割れする確率 |
| 1年 | 13.57% (90本/663本) |
| 3年 | 0.81% (5本/616本) |
| 5年 | 1.81% (10本/552本) |
| 10年 | 0%(0本/322本) |
※2022年時点
表の見方は、1年前から運用されていたファンドが663本あり、その中で利回りがマイナスだった投資信託の本数が90本だったという見方をします。
3年だったら、3年前から運用されていた投資信託が616本あり、3年間運用して利回りがマイナスなファドは5本という意味です。
ちなみに、10年前から運用されている投資信託に至ってはなんと元本割れしているファンドは1本もありません。

これを頭で理解できていれば、始めるタイミングにそこまでこだわる必要がないことがわかるでしょう。
長期投資を前提に考えるのであれば、投資信託は非常に魅力的な設計になっています。
どのタイミングで買えばいいかということを考える時間があるのなら、その時間を使って、どの商品を購入するか検討することに時間を使ってくださいね。










