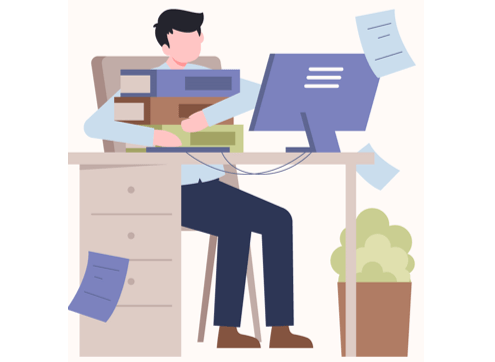初めて投資信託を購入しようとしている方によく聞かれるのが、「どうやって投資信託を勉強すればいいですか?」という質問です。
色々と書籍を紹介しているブログなどがありますが、どうも私にはピンときません。
私も色々と投資信託に関する書籍は読んできましたが、書籍に書かれていることは、知識を増やすための勉強にしかなりません。
車を例に例えると、公道で車を運転できるようになりたいのに、エンジンの仕組みやタイヤの付け替え方の知識が書かれているようなものです。
あなたはそれで満足できるでしょうか?
日本人は特に知識を身に付けるための勉強が好きな人が多く、実践で役に立たない知識ばかり、頭に詰め込んでいる人をよく見かけます。
あなたが自転車に乗れるようになりたいと思ったときに、自転車の乗り方を本で何時間もかけて頭に詰め込んでいる人と転びながらも自転車に何時間も乗ってみる人がいたら、どちらが早く上達すると思いますか?
言うまでもなく、あなたにもわかったと思います。
今日、私がお話しするのは、頭に知識を詰め込むための勉強法ではなく、実際に投資で「成果を出す」ための勉強方法です。ぜひ参考にしてください。
おすすめの勉強方法のステップ
①投資信託でよく使う言葉を覚える
まず、投資信託でよく使われる用語がわからなければ、話になりません。
ただ、書籍等を購入すると、普段は絶対使わないような用語が羅列されており、勉強のやる気をそぐ以外の何にもなりません。
ですので、まずは必要最低限の用語を覚えてもらい、あとはわからない言葉が出てくるたびに調べるのがおすすめです。
では、その必要最低限の用語とは何なのか?
少なくとも私のブログで書かれている内容がわかるようになれば、普通の投資家よりも間違いなく投資信託について詳しくなっています。
定期的に色々な記事を読んでみてもらうとよいですが、まず初心者の方におすすめするのであれば、このあたりから始めるのがおすすめです。
【完全保存版】他では絶対教えてくれない投資信託の正しい選び方
プロは必ず知っている。投資信託で稼ぎたいなら、必ず知っておきたい常識8選
無料ファンド相談から見えた。多くの人が気づいていない投信運用で成果を阻む9つの誤り
②プロが投資信託を分析している視点や考え方を盗む
私も投資信託を購入し始めたころは、何を基準に購入すればいいか全くわかりませんでした。
しかし、プロのファンドマネージャーや実際に投資信託で莫大な富を気づいている方の話を直接聞く中で、投資信託を分析する視点や考え方が身についていきました。
今回、このブログには、300以上の投資信託の分析記事を載せており、私が投資信託を選定するときに必ず確認しているポイントを記載しています。
全部読めとは言いませんが、10記事くらい読めば、最低限ここは押さえておいたほうがいいというポイントはわかるようになると思います。
ですので、勉強方法の第二ステップとして、「プロの分析している視点や考え方を盗む」ようにしてください。
③他人の失敗から学ぶ
投資を始めようとしている人は、どうすれば資産が増えるかばかりに目がいきがちです。
その結果、投資で一番大事なリスクを見極める視点が抜けてしまうことがよくあります。
そこで、実践してほしいのが、投資信託で失敗した人の話を聞くことです。
なぜその人は失敗したのかを事前に知ることで、自分は同じ失敗はしないようにしようと思えるようになりますし、そうなれば、投資で一番やってはいけない大損をすることもなくなるでしょう。
④早速購入
上記、3つのステップをクリアしたら、自分が投資してみたい!と思う投資信託を早速購入してみてください。
金額は10万円くらいがいいでしょう。
あまり金額が小さすぎると、投資している感覚にならないため、損をしたら嫌だと思えるレベルの金額を投資することで、強制的に、真面目に学ぶ環境を作れます。
まだ勉強が足りていないので、投資に踏み切れませんという人がいますが、いつまでたっても、勉強が足りることなどありません。
何年も投資をしている私でさえ、日々学ぶことがたくさんあります。
ですので、あれこれ考えずに一歩踏み出すようにしましょう。これが勉強方法の第四ステップです。
⑤わからないことはプロに聞く
なかなか身近に投資のプロがいないからこそ、ネットで情報収集をしているのだと思いますが、最後はやはり投資を専門にしている人の意見を聞くのが一番近道であることは間違いありません。
私も、大学生のころから、多くの投資の先輩の話や考え方を聞き、成長していきました。
今は、多くの投信ブロガーの方がいますので、ブログを読むだけでも勉強になりますし、このブログであれば、無料でファンド相談ができるサービスも行っています。
誰にも聞かずに判断して失敗してきた人をたくさん知っていますので、お気軽に無料相談サービスを活用してください。
【参考】投資信託で失敗した人たちの事例集
証券会社の営業マンの言いなりになって、投資信託を買ってしまったAさん
Aさんは親から受け継いだ資産を5000万ほど保有しており、将来への不安から何か新しい投資先を探していました。
そこで知り合ったのが、某証券会社のZさんです。
Zさんは、人柄がよくお話も上手なので、この人なら信頼できると思ったAさんは、Zさんの進める投資信託を購入することにしました。
購入した商品はいわゆる毎月分配型の商品で、お金を預けておけば、毎月臨時のボーナスが入ると言われ、つい買ってしまったようです。
購入後、確かに毎月10数万円のお金が振り込まれていたのですが、たまたま私と知り合って、投資信託の現在の基準価額を見てみると、購入時より20%近く下がっていました。
基準価額が下がったときの分配金は投資元本から支払われますので、喜んで受け取っていた10数万のお金は自分が投資した資金の中から払い出されており、実質的には損をしていたのです。
Aさんはとても悔しそうにしていましたが、その後私がまともな投資信託をご紹介したので、今では損失を取り戻しています。
ここでの教訓は、証券会社の営業マンや銀行の窓口の人間はあてにならないということです。
彼らにも仕事上の目標があり、会社にとって利益が出る商品(投資家が損をしやすい商品)を一定数販売しないといけません。
その結果、投資家にも売りたくない商品を売っているのが現状です。
どんなに人のいい営業マンだったとしても、金融機関の営業マンのことをそのまま信じるのは絶対にやめましょう。
昨年一番値上がりした投資信託を購入して失敗したBさん
投資を始めたばかりのBさんは商品選定の方法がよくわかりません。
そこで、昨年値上がりした投資信託のランキングを見てそこから選ぶことにしたそうです。
ランキングを見ると、昨年度の値上がり率が1位になっていた投資信託は+103%となっていました。
そこで、Bさんは「ランキング上位にランクインしているなら、今年も大きな値上がりが期待できるんじゃないか」と思い、購入してみることにしたとのこと。
その結果、購入1カ月後には、-30%の大暴落。パニックになったBさんはこれ以上損はできないと思い、投資信託をすぐに売ってしまったのです。
ここでの教訓は、株でも投資信託でも値上がり過ぎた銘柄や、値下がり過ぎた銘柄は、かならず調整が入ります。(正常な水準まで価格が戻ること)
特に、昨年1年間のパフォーマンスが圧倒的に優れているような投資信託だとかなり高い確率で価格が下がります。
ですので、価格が上がり過ぎている投資信託というのは要注意であり、継続して高い運用実績を出しているのかは必ず確認しないといけません。
私は、どんなに少なくとも3年の実績は確認します。5年、10年の運用実績があるのであれば、そちらも確認しておいたほうがいいでしょう。
人気ランキング上位の投資信託を購入したCさん
同じく投資初心者のCさん。どのように商品選定すればよいかわからなかったので、人気ランキングを見て、ランキング上位の投資信託に分散投資をしてみることにしました。
しかし、人気ランキング上位の投資信託に投資をしたにもかかわらず、1年間の運用実績は微減。
人気の銘柄だからこそ、1年後の値上がりを楽しみにしていたCさんはとても残念に思ってしまいました。
これもよくある話ですね。人気ランキング上位に投資をしたら、全然増えなかったというパターンです。
ランキングというのも誰が作ったランキングかというのは、非常に重要です。
例えば、証券会社が自社で取り扱っている商品のランキングを作っている場合、かなり操作されていると考えたほうがいいでしょう。
人気ランキングと言いながらも、実際は、証券会社の営業マンが会社の命令であの手この手を使って、大量に販売した酷い投資信託が上位にランクインしていることが十分にあり得ます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
投資信託の勉強法にも知識が増えるだけの勉強方法と成果が出る勉強方法があります。
ぜひあなたには、成果が出る勉強方法で今後も学んでいってほしいと思います。
投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。
しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。
>>まさか考えたことがない?運用が成功するか失敗するかすべてのカギを握る投信運用の出口戦略最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。
今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。
>>なぜ私が投信運用に限界を感じたのか。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点