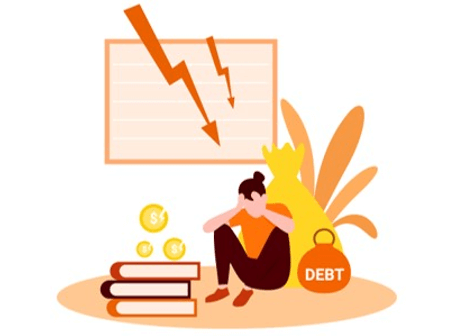10年平均利回りランキングは多くの方から好評をいただきました。
一方で、最近のファンドが全く入っていないので、最近設定されたファンドはどうなんだ?というお声をいただくことがあります。
そこで、3年以上運用実績があるファンドの中でのランキングを新たに作成しました。
3年というのは明確に何か根拠があるわけではないのですが、投信業界ではよく、新設ファンドは3年は様子をみようという格言めいた言葉がありますので、3年としています。
そこで、今回は3年以上、運用期間があるファンドの中でのパフォーマンスランキングを見ていきたいと思います。
10年平均利回りのパフォーマンスランキングと比較して、果たしてどんなファンドがランクインしてくるのでしょうか?
あなたもまだ知らないような隠れた優良ファンドが存在しますので、ぜひ参考にしてください。
国内大型株式ファンドの3年平均利回りランキング ベスト20を発表!
国内大型株式ファンドは現在391本あります。その中で、2020年11月~2023年10月の3年間でリターンの高かった上位20社をランキングにしました。
中には、純資産総額が非常に小さく、今から投資をするのは、あまりおすすめできないものも含まれます。
そのため、1つ1つ全ファンドを見るのも大変だと思いますので、少なくとも、純資産総額が100億円以上あるファンドのみに絞り、私が分析記事を作成しました.
以下のリンクが張ってあるページが該当するファンドになります。
| 順位 | 銘柄 | 3年平均利回り |
| 1 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 42.14% |
| 2 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 34.70% |
| 3 | ダイヤセレクト日本株オープン | 28.43% |
| 4 | 新光 日本インカム株式ファンド(3カ月決算型) | 27.95% |
| 5 | ダイワ 金融新時代ファンド | 27.38% |
| 6 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 25.49% |
| 7 | 大和住銀 DC国内株式ファンド | 23.67% |
| 8 | みずほ好配当日本株オープン | 23.30% |
| 9 | 三井住友DS 日本バリュー株ファンド 『愛称:黒潮』 | 22.84% |
| 10 | 日本好配当株オープン | 22.04% |
| 11 |
好配当日本株式オープン 『愛称:好配当ニッポン』 | 21.45% |
| 12 |
DIAM 割安日本株ファンド | 21.43% |
| 13 |
日本好配当株投信 | 21.34% |
| 14 |
JPX日経400アクティブ・プレミアム(毎月) 『愛称:JPXプレミアム』 | 20.89% |
| 15 |
割安株ジャパン・オープン | 20.80% |
| 16 |
損保ジャパン・グリーン・オープン 『愛称:ぶなの森』 | 20.70% |
| 17 |
三菱UFJ バリューオープン | 20.22% |
| 18 |
日本好配当利回り株 | 19.89% |
| 19 |
フィデリティ・日本配当成長株 | 19.07% |
| 20 |
ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称:底力』 | 18.96% |
※2020年11月~2023年10月
※為替ヘッジ無のファンドが対象
※分配型、資産成長型など同じファンドで2つのファンドがランクインしている場合、パフォーマンスの高いほうを採用。
※通貨選択型のファンドは為替の影響を大きく受けているので、除外しています。
参考までにTOPIXに連動するインデックスファンドの利回りは約15%程度、日経平均に連動するインデックスファンドの利回りは約13%前後となっていますので、インデックスファンドよりも成績の良いアクティブファンドは多数あることがわかります。
インデックスファンドがかなり強い米国株や先進国株とは少し違いますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
予想以上に聞いたことがないファンドの名前が多かったのではないでしょうか。
結局、銀行や証券会社の営業マンは、自分たちが儲かる商品を売ってきたため、本当に良いファンドというのが見過ごされてしまっているわけです。
ただ、パフォーマンスだけをみていると、純資産が小さくすぐに償還を迎えてしまうリスクもあります。
ですので、ある程度の規模は確保しつつもパフォーマンスが優れたファンドに投資をしていくというのが一番理想的でしょう。
3年平均利回りと合わせて、10年平均利回りランキングも参考にしてください。
国内大型株式ファンドのおすすめは?10年平均利回りランキング ベスト20を発表!
投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。
しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。
>>ここまで考えるのが本当の資産運用。多くの投資家が考えられていない投信運用の出口戦略とは最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。
今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。
>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点